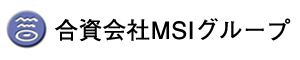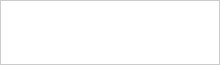■4. レスポンスの追求
バブル期のカネ余り状態の経済下では、企業や商品ブランドのイメージを打ち出すだけのイメージ広告の打ちっぱなし状態が当たり前でした。もちろん、今ではそんなことができる余裕を持っている企業はほぼなくなりました。しかし、それは意識的にそのようにしている企業が少なくなっただけのことであって、後述する中小零細企業の広告出稿実体の“あるある”で述べるように、単に戦略性が完全に欠如しているために、考えもせず、戦略性ゼロのイメージ広告のようなものを打ち続けているケースはそれなりに今でも存在し続けています。
バブル期ぐらいまで時計を巻き戻し、イメージ広告全盛の時代から、コスパ重視のレスポンス広告に至る変遷を少々振り返ると、今、広告出稿にどのようなスタンスで向き合うべきかを理解する上で参考になります。
(1)CIの隆盛
かつて、CIと言う考え方が持て囃されたことがあります。CI(コーポレート・アイデンティティ)は、企業が外部に与えるイメージを統一し、分かり易くするところに意義がありました。CIは、実際には…
★MI(マインド…):社員の考え方や経営方針の統一
★BI(ビヘイビアラル…):社員の行動や企業活動のあり方の統一
★VI(ビジュアル…):企業のロゴマークなどの使い方の統一
の三分野を統合したものでした。
この三分野の統一は非常に意義あるものと弊社でも考えていますが、バブル経済下やバブル経済直後の時代のCI活動はロゴマーク関係の規定策定や事業ドメインに合致したキャッチコピーの案出などに殆どのケースで終始してしまったように見えます。
また、打出したイメージが、自社が狙うターゲットのステークホルダー群にとって、「自分のニーズを満たしてくれるような」、または「自分にとって好ましく思える」、「自分にとって、(取引と言う)関係性を構築したい」と感じさせるものであるのか否かは、CI活動の上で、余り議論されていなかったようにも思えます。詰まる所、相手側からの目線を考えて作ったものではなく、単に就活学生の自己PRの企業版と言うような位置づけでした。
本来経営論的に見て素晴らしい考え方であるCIが、このような混迷しか生まなかった最大の理由は、大手企業がCIを進めた理由が、バブル期に余った金を使う口実として、大手広告代理店のCI採用の提案に乗った結果だからと考えるべきでしょう。よく考えてみると分かりますが、大手広告代理店は経営コンサルティング会社や研修会社ではありません。クライアントの大手企業のロゴマークやキャッチコピーを作ったり、企業イメージを漠然と謳うCMづくりは幾らでもできますが、社員の頭の中や行動を変えるようなことはできないのが当然です。流行ったCIも結局は広告代理店の儲けのための戦略に過ぎませんでした。CIのうち、広告代理店が手に負えないMIもBIも置き去りにされて、結局はVIしか機能しないうちに終わったことになります。
MIとBIは皮肉にもインターネット普及後の世界で漸く意識されるようになって来たと見ることができます。 企業のコンプライアンスが叫ばれて、それが明確に法制化されたのと並行して、ネット社会になったことによる企業監視や内部告発の容易性が実現しました。その結果、初めて、MIやBIが企業によって本気に取り組まれる環境が整ったと見ることさえできるのです。
(2)イメージ広告からレスポンス広告への遷移
本来、当時のイメージ広告の隆盛は、顔の見えない多くの顧客に向けて自社主体のメッセージを届けるための、ランチェスター戦略論でいう「確率戦」に適した手法です。それに真向ぶつからず、局地戦で挑む中小零細企業では、多くの場合、顧客は顔の見える関係でいられるはずですから、直接個々の顧客に対して、購買を訴求すれば事足ります。これが中小零細企業において、イメージ広告よりもレスポンス広告を重視するべき最大の根拠です。
さらに付け加えると、大手企業の場合、イメージ広告は顧客に対するものでさえないケースも多々あるものと考えられます。イメージ広告の大手企業での役割には、(B2Cの高級品を扱うブランド広告以外は)見えない株主に自社の存在感や躍進感を伝えることも含まれているのです。当然ですが、社外に不特定多数の株主が存在しない多くの中小零細企業で、このようなことを行なう必要はありません。
こうした水面下の認識を誰もが知る常識に変えたのが、神田昌典の処女作、通称“ピンク本”(と続編の通称“青本”)が大ヒットしたことです。レスポンス広告で収益を上げることを明確に意識する中小零細企業が増えてきました。その後、セールス・コピー・ライティングを一生モノのスキルとして販売する“情報商材”まで流行るほどに、「広告で売る」ことは常識的になりました。それは紙であれ、ウェブであれ、コストがかかる情報発信には、コスパが求められる時代になったということです。
(3)アクセス解析の浸透によるコンバージョンの追求
コスパの測定は、ネットの普及によってよりさらに先鋭化しました。PPC広告なら出稿のコスパがいきなり分かり、さらにその先のランディング・ページからの動きは、自社ウェブサイトのアクセス解析で追えるようになったのです。
最終的にウェブに入り込んだアクセスのコンバージョンの形が問い合わせであれ、資料請求であれ、購入であれ、どのような人がどのような規模でコンバージョンするかを分析することが、(あくまでもきちんと取り組んでいる)中小零細企業においても当たり前になりました。
アクセスの状況は時々刻々と変化していきますから、本来、特に機動性が主要な強みになる中小零細企業において、自社内で大まかにでも分析し続けることが大事です。しかし、経営者自身もウェブどころかICT系の基礎知識を持ち合わせていず、ウェブ系の業者に高い費用を払って分析を辛うじて行なっているケースが非常に目立ちます。余程自社のビジネス・モデルとそのマーケティング戦略に精通した外部業者でなくては、殆どカネを溝に捨てている状態になっているように弊社では認識しています。
当然ですが、広告のコスパを追求するには、ターゲットのニーズにきちんと合致する広告を出稿するのが最も重要なカギです。それも、紙や電波媒体に比べて、広告情報の他ソースのものとの競合が非常に激しいのがネットが普及した後の時代ですから、ターゲットのニーズやベネフィットの想定は、以前より精度高く求められることになります。その状況に業界構造もよく分かっていないようなウェブ業者を巻き込んでも、役に立つわけがないと考える方が普通でしょう。
その後、SNSの普及から「無料の広告」としてSNS利用に打って出た中小零細企業も、コンバージョン視点から厳密に見ると殆どが失敗しました。そうしたSNSアカウントでの記事アップの使い方ではなく、中小零細企業は、SNSのPPC広告をまず活用すべきでしょう。SNSのPPC広告は、米国で再三そのレスポンスの少なさが騒がれていますが、そのターゲティングの機能は非常に優れています。その意味でも、やはり、精度の高いターゲット設定やニーズ、ベネフィットの設定がより重要になった状態であるのに、ついて行けていない広告出向者が多いので「レスポンスが少ない」と言う不満が出るという風に考えるべきです。
コンバージョンが測定しやすいのは主にウェブの世界の話です。ですので、既存の紙や電波などのメディアの広告出稿で獲得できたリード(≒見込客)的な存在も、基本的にはウェブに誘導する形にすることで、情報の収集・分析やその蓄積などが可能になって来ます。その意味で、コンバージョンが重視されるようになればなるほど、自社ウェブは各種の広告出稿を中心とする外部への情報発信を行なう上でのカナメとなるのです。今後スマホの存在が大前提となった社会において自社アプリの活用などもリード収集に採用されるでしょうが、基本的にオンラインの世界の中で完結するリード収集なら余計のこと自社ウェブがカナメになっていきます。その意味で、中小零細企業でも、自社ウェブをきちんと使いこなすことは、広告出稿も含めた外部への情報発信の活動を行なう上で必須になったと考えられます。